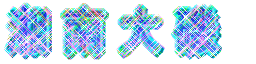「湘南」とは、日本古来の地名ではなく、外来語である。
中国・湖南省の瀟水・湘江や洞庭湖一帯の風光明媚な地を指す「瀟湘湖南」に由来する。
「中国湖南」に対する憧れは漢詩を通じて日本にも早くから伝わり、南北朝時代に復興した苔寺(京都・西芳寺)茶室にも「湘南亭」の名がつけられている。
こうした憧れの名前をいち早く明治時代につけていた村がある。現在の神奈川県相模原市(旧、津久井郡城山町)「湘南村」である。明治22年(1889)の市町村制施行にともない、それまで独立した村であった小倉、葉山島が合併することになり新しい村名として「湘南村」誕生の秘話へとつながる。
当時は合併する市町村名を一字づつ組み合わせて新しい名前にする場合が多かった。東京の大田区が旧大森区と旧蒲田区のように。
ところが小倉と葉山島では小葉(こっぱと読める)や小島(隣に大島村がある)では面白くないと、なかなか決まらなかった。当時の連合戸長の馬場健二氏が県庁に呼ばれ命名をを迫られ、当時の文人たちが相模川のことを湘江とも呼んでいたのを知って、湘江の南側にある二つの村が合併するのだから「湘南」と発案したのが湘南村誕生記です。
かくして馬場健二は湘南村初代村長となりました。しかし、昭和30年の再合併で湘南村の名は消えてしまいました。
現在の湘南と云われている地域の名称は、大磯にそのいわれの碑が建っている。
国道一号線沿いの大磯町役場の近くに、鴫立沢と云う所がある。ここは、西行法師が「心なき 身にも哀れは 知られけり 鴫立沢の 秋の夕暮れ」という三夕の歌の一つを詠んだところで、寛文4年(1664)頃、崇雪と云う人が西行のこの歌を慕ってこの地、鴫立沢に草庵を結び標石を建てた。この草庵が現在にも伝わる鴫立庵であり、その標石には「著盡湘南清絶地」(あきらかに湘南は清絶をつくす地)と刻まれていて、この地の景勝を讃えたのが湘南の始まりのようです
大磯の古い風景写真